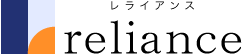2017年のノーベル平和賞に国際NGOのICANの「核兵器廃絶国際キャンペーン」が選ばれました。彼らの活動が核兵器禁止条約の国連採択に多大な貢献をしたことは言を待ちません。
しかし、その後の経緯を見ると各国が批准する見込みが立たないようで、それは核保有国や関係国だけでなく、核を保持していない国でも同じようです。国連で採択されることと、それを各国が批准することは別の懸案のようです。
国連で採択されても、それぞれの国では批准に至らないのであれば、そんな採択にどのような意味も意義も見いだせないという見方から、国連の存在意義が問われ始めて久しい中、核保有について国連では否定的な採択がされる傾向が強まり、理想と現実の乖離が益々進み始めていると理解できます。

現実的な検証のない核論議
世界的な傾向としても、核兵器の保持については国連で反対をして、国内で批准するというスタイルが一般化してきている中、ほとんど現実的な、且つ具体的な議論や検証をしている例はほとんどなくなっているように感じます。例えば核兵器を廃止したとして、大国や強国、核開発国では大戦が起こらないということをしっかりと論証している例はほとんど見ません。ほとんどが「通常兵器にも抑止力は働く」程度の論調で有れば、そんなものは検証とは言いません。
「北朝鮮が核兵器開発がなくて、中国に反旗を翻すことができたのか」
「第二次大戦末期、日本に核兵器があっても、日本の都市への無差別爆撃は行われたか。広島・長崎に原爆が落とされたか」の問いにどのような答えが用意されているのでしょうか。

核兵器が壊滅的な結果に繋がることに間違いはないでしょう。しかし世界にこれほど核が瀰漫しているにも関わらず、最悪の結果が起きていないのはなぜでしょうか。やはりそこには現実的な「抑止力」が働いていたことは否めない事実でもあります。では核兵器さえ保持しなければ絶対安全なのか。それに関しては核兵器の国際条約の歴史が答えを出しているようにも思えます。
ABMが有名無実化した世界の中で
2002年まで世界には核兵器による力の均衡を保つためのルールとして“ミサイル防衛を制限する”条約がありました。「弾道弾迎撃ミサイル制限条約(ABM)です。これは不思議な条約なのですが、簡単に言えば「自国が滅びる可能性を各国が担保する」という考えです。相手の放った核兵器を迎撃する機会を減らすことを約束し合うということは、わざと防衛能力を落として、自滅する恐怖を自らの国に残しておくことでしか核の抑止力が高められないという変な理屈なのですが、これが当時の現実的な対応として難産の末、生み出された知恵ではありました。しかし、この条約を締結しない国々が次々に核保有を進めることで、その実行が約束されないとの判断の下でアメリカが脱会した為、その後同国のミサイル防衛には多額の予算が割かれるようになり、多国はその防衛技術を越えなければならなくなり、益々防衛予算を吊り上げる悪循環が起こりました。

旧ソ連からロシアに移行した時にも同様の変化がありました。プーチン大統領の論理は「核は大変廉価でありながら効果的な防衛兵器である」でしたが、それがもたらした結果は世界が知るところです。
本当に日本が果たすべき役割とは
しかしそんな経緯にも関わらず相も変わらず国連やメディアでは「核」だけを全面廃止するような主張が支持され、現実的に判断しなければならない各国の政治判断で批准をしないような形だけの議論が繰り返していては、畢竟何も進むことはありません。
残念ながらその意味ではICANは今後ノーベル賞を受賞したことで、なにがなんでも非核主義にならざるを得ず、核を持つ現実的な問題点に向かう事は期待できず、核拡散条約に入っていないノルウェーや日本に対しての圧力団体として、グリーンピースと同じような立ち位置になってくることが容易に想定できますので、問題の解決には役に立つ存在としての位置づけは遠くなってしまいますので、それに代わる現実路線で話し合える仕組み作りが重要ですが、現状ではやはり各国の外交問題の案件として位置付けて行くほかはないのかも知れません。

且つて黒澤明監督は1955年に「生き物の記録」という映画で、核兵器の恐怖を漠然と感じている人々に対する警鐘を鳴らしました。世界はその後、それを持たずに核の時代の平和が保てるのかについて半世紀の冷戦時代に於いて様々なシミュレーションを繰り返しましたが、国際会議の舞台や戦争に目を背けて行けた日本社会だけはそこで止まったままになってしまいました。すでに国際会議の舞台での反核の真意が揺るぐ中、日本は本当に被爆国として発言するのであれば、より現実的な研究がなされなければならない。それが、戦争や原発事故で命を落とした同胞に対する私達の責任でもあると考えます。